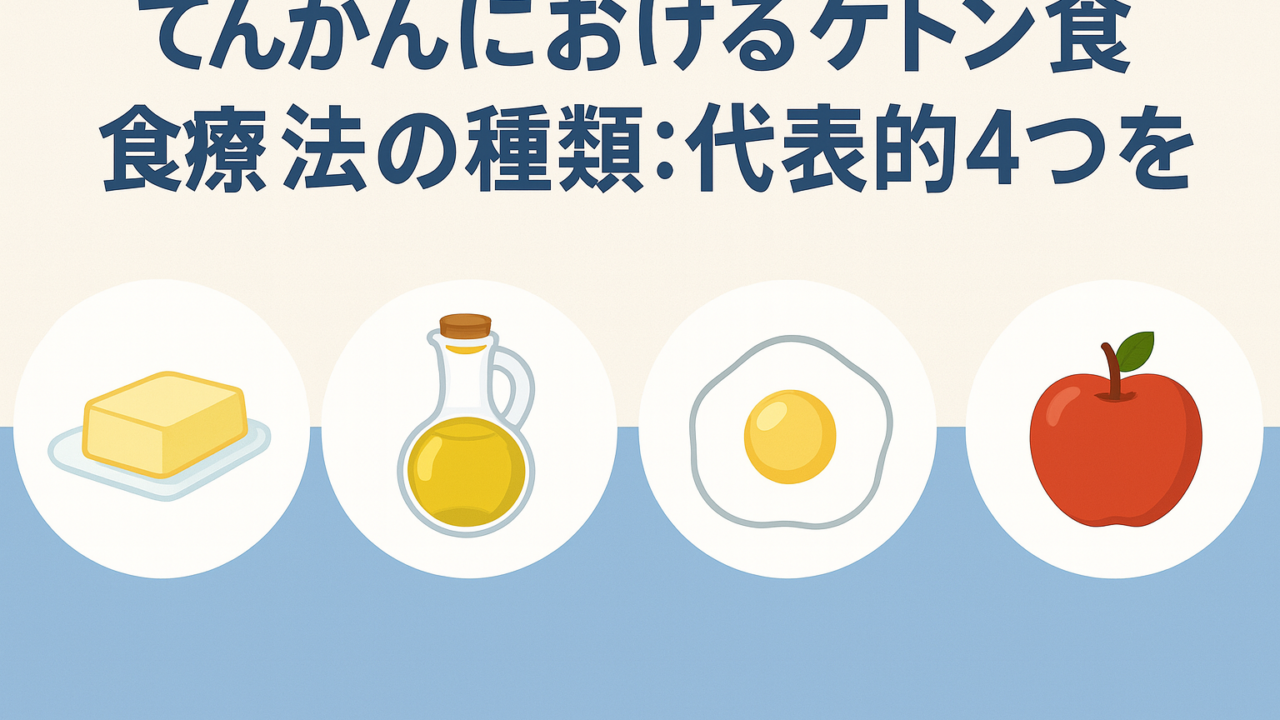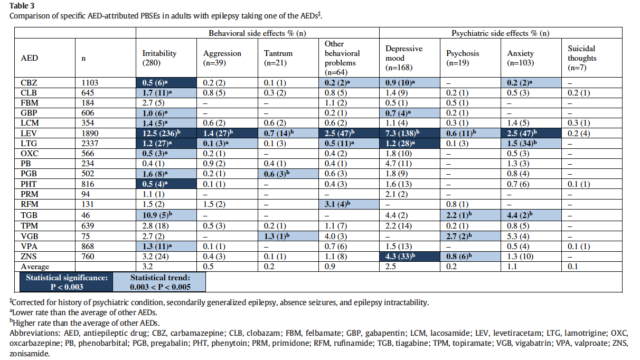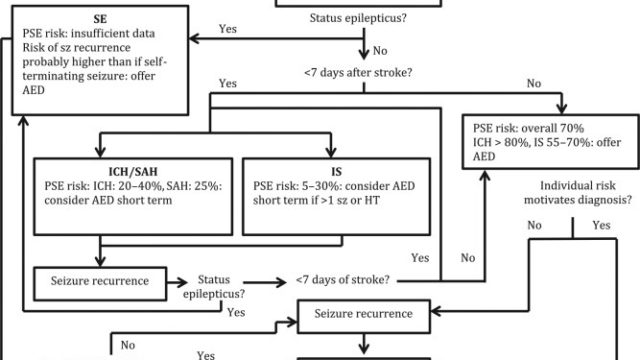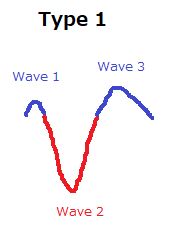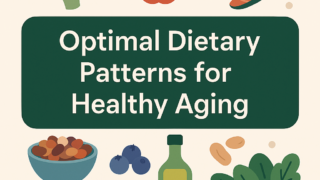ケトン食療法(Ketogenic Dietary Therapies, KDTs)は、薬剤抵抗性てんかんに対する確立された非薬物療法です。古典的なケトン食(classic KD)は1921年に導入されて以来100年以上の歴史がありますが、近年は複数のバリエーションが開発され、患者背景に応じた柔軟な選択が可能になっています(Kossoff et al., 2018)。ここでは、現在用いられている代表的な4種類のケトン食と、その効果について整理します。
Contents
古典的ケトン食(Classic KD)
-
特徴:脂肪と炭水化物+タンパク質の比率を4:1(または3:1)とする厳密な食事療法。脂肪が全体の90%を占める。
-
利点:発作抑制効果が高く、特に小児の難治性てんかんで有効性が証明されている。
-
課題:食事制限が厳しく、長期の継続が難しい場合がある。
中鎖脂肪酸(MCT)ケトン食
-
特徴:MCTオイル(C6–C12脂肪酸)を全体の60%とする。MCTは長鎖脂肪酸よりも効率よくケトン体を産生。
-
利点:食事の脂肪比率を下げられ、炭水化物やタンパク質の摂取が比較的自由になる。
-
課題:消化器症状(腹痛、下痢など)が起こりやすい。
修正版アトキンス食(Modified Atkins Diet, MAD)
-
特徴:炭水化物を10–20g/日まで制限するが、厳密な比率やカロリー制限は不要。タンパク質・水分の制限もない。
-
利点:調理や家庭での実施が容易で、小児から成人まで広く適応可能。
-
エビデンス:複数の臨床研究で有効性が確認されており、特に成人てんかん患者における実用性が高い(Kossoff et al., 2018)。
低GI療法(Low Glycemic Index Treatment, LGIT)
-
特徴:炭水化物摂取を制限しつつ、グリセミック指数(GI)が50未満の食品に限定する。炭水化物は40-60g/日まで。
-
利点:血糖値の安定を重視し、食事の自由度が高い。患者の生活の質(QOL)を保ちやすい。
-
効果:薬剤抵抗性てんかんにおいて発作抑制効果が報告されている。
臨床効果と適応
-
有効率:いずれの食事療法でも、約40〜50%の患者で発作が50%以上減少することが報告されている。
-
特に有効な症候群:
-
GLUT1欠損症候群(Glut1DS)
-
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ欠損症(PDHD)
-
ドラベ症候群
-
ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん(Doose症候群)
-
結節性硬化症関連てんかん
これらでは60〜70%の高い奏効率が示されている。
-
作用メカニズム
ケトン食の抗てんかん作用は多面的であり、主な仮説として以下が挙げられます:
-
ケトン体による神経代謝改善
-
神経伝達物質バランス(GABA増加、グルタミン酸抑制)
-
ミトコンドリア機能の改善
-
腸内細菌叢の変化による抗痙攣作用
まとめ
ケトン食療法は、古典的KDからLGITまで複数のバリエーションが確立され、患者背景やライフスタイルに応じた柔軟な治療選択が可能になっています。今後は、てんかん以外の神経疾患や代謝性疾患への応用も進んでおり、個別化医療の一環としての役割が期待されています。
参考文献
-
Kossoff, E.H., Zupec-Kania, B.A., Auvin, S. et al. (2018) ‘Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: Updated recommendations’, Epilepsia Open, 3(2), pp. 175–192. doi:10.1002/epi4.12225.
-
Zhu, H., Bi, D., Zhang, Y. et al. (2022) ‘Ketogenic diet for human diseases: mechanisms and clinical implementations’, Signal Transduction and Targeted Therapy, 7, 11. doi:10.1038/s41392-021-00831-w.